
2010年10月29日 (金) 掲載
フルートやギターなど数種の楽器を操るマルチ奏者であり、その歌声で幅広いジャンルのリスナーを惹き付けるシンガーでもあるマイア・バルー。彼女はその強烈な個性で現在各界から注目を集める存在だ。父は現代フランス音楽のレジェンドであるピエール・バルー。自身のサラヴァ・レーベルを率いて数々の名作を残してきた彼と日本人の母のもとに生まれた彼女は、パリと東京を行き来しながらさまざまな音楽文化を吸収してきた。
そんな彼女とブラジル人打楽器奏者シロ・バプティスタのコラボレーションが、11月3日(水)に恵比寿リキッドルームで行われる“Hennessy artistry Presents J-WAVE Gilles Peterson’s “WORLDWIDE SHOWCASE 2010”~Galaxy Session~”で実現する。そのコラボレーションへの思い、そして彼女のこれまでの歩みについてロングインタビューを決行。
お生まれは東京なんですか?
マイア・バルー:そうです。生まれたのは青山の病院だけど、最初に住んでたのは麹町だったかな?でも、生まれてすぐにフランスに行っちゃったんですよ。
フランスにはどれぐらいの期間、いたんですか。
マイア・バルー:行ったり来たりですね。ピエール(・バルー)はサラヴァや芝居をやっていて忙しかったので、私もフランスにいたことが多かったんです。ただ、大きく言うと、15、16歳まではフランスのほうが多かったかな。
住んでいたのはパリですか?
マイア・バルー:パリです。パリの5区。ルクセンブルク公園とかバンテオンがある観光地。石畳の市場の道があったりするような。5区にはけっこう長く住んでいたので、近所のたばこ屋さんのおばちゃんとか肉屋のなんとかさんとか、昔から仲良くしている人たちがたくさんいたんです。
じゃあ、子どものころからフランス語と日本語の両方で生活している?
マイア・バルー:そうですね。両方話してました。教育についてはすごく考えてくれていたみたいで、それに関しては本当に親に感謝してます。母も父も一致していたのは、日本語というのは小さいころに習っておかないと、あとからは勉強できないと。漢字とか読み書きとかね。フランス語はABCさえわかれば後から勉強できるけど、日本語はできないからって。パリでは日本人学校に通っていたんです。だから、教育は全部日本語。だけど、学校から一歩出ればフランスだし、家に帰ってもフランス語。そういう意味ではすごくバランスが良かったのかなって思っています。
子どものころはどんな音楽を聴いていたんですか。
マイア・バルー:家ではいつも生の音楽が流れていたんですよ。ピエールの友達はだいたいラガーマンかミュージシャン、もしくは役者さんで、絶えず家に誰かがいる感じで。みんな食卓に集まってはなにか演奏してたり、リハーサルしてたり、そういう環境でしたね。あとはミュージシャンが来て「これを聴いてくれ」ってピエールに音源を渡していたりね。そういう環境が自然にあったんです。なので、自分で音楽を聴きだしたのはちょっと遅いと思います。14、15歳ぐらい。はじめて自分から「いいな」と思ったのは、ピエールがプロデュースしていたビーアっていうブラジル人の歌手。あと、私には腹違いのお兄ちゃんがいるんですけど、彼はサラヴァでも働いていて、幅広く音楽を聴いていて。ロックからジャズまですごく詳しくて、いろんな音楽を聴かせてくれたんですよ。ジャズだとチェット・ベイカーとか、ビル・エヴァンスとか。
じゃあ音楽的な環境としてはかなり恵まれてますね。
マイア・バルー:いやもう、最高の環境です。
そういうなかで自然と“自分でもなにかを表現したい”という欲求が高まっていったんですか?
マイア・バルー:そうですね。ただ、あまりにもいい音が生活のなかに溢れていたから、「わざわざ自分でやることないんじゃないの?」って逆に思っちゃって。中学生のころは生物学者になりたかったんですよ。虫や動物が好きなので、そっちに関わることがしたいって思いもあったんです。そうは言いながらも、私は本当にハイハイする前からライブに連れて行ってもらってて。まだヨタヨタしているのに前の椅子にしがみついてずっとステージを見ているような赤ちゃんだったみたい。それとね、ライブがあると、ピエールは必ず私をステージにあげるんですよ。いつも「歌え」って。それがすごく嫌で、“きたきた!”と思うと会場の隅っこに隠れたり、テーブルの下に隠れたりしてね(笑)。まぁ、シャイな子だったんですよ。でも、だんだん(音楽が)楽しくなってきて、気づいたら「ちょっとマイク貸してよ」ぐらいの感じになってた(笑)。もともと6歳のころからクラシックピアノをやっていて、楽器にはずっと触れていたので。
“音楽をやりたい!”と具体的に思ったのはいつごろだったんですか。
マイア・バルー:ビーアのレコーディングのためにピエールたちがブラジルのリオ(・デ・ジャネイロ)に行ったことがあって、私も付いていったんですよ。そのときのレコーディングでフルートを吹いている女性がいて、「ああ、これをやりたい!」って思ったんです。初めて自分でやりたいと思ったのがフルートだったんですね。それが16歳のころ。
なんでフルートだったんでしょうね?
マイア・バルー:なんでだったんだろう?そういうのって、やっぱり出会いとタイミングだから。私の場合、上手いプレイヤーを聴くとやりたくなっちゃうんですよ。だからそのとき演奏していたのがトランペットの人だったら、トランペットをやりたくなっていたかもしれない。そこは今も変わらないですね。「クラリネットやりたい」とか「サックスやりたい」とか、すぐに影響されちゃう(笑)。
そのころは他の国にも行ってたんですか。
マイア・バルー:個人的に行ったのと両親と行ったのと両方ですけど、いろいろ行ってましたね。両親と行ったのはキューバと中東、あと東南アジア。ピエールがキューバの映画学校で教えていたんで、それについて行ったんですよ。11歳ぐらいかな。
11歳でキューバに行ったらかなりのインパクトがありますよね。
マイア・バルー:ありましたね!私の妹なんて1歳だったし。今はけっこう観光地だけど、そのころは子どもをつれて行くな、って周りに言われるぐらいだったから。
感受性の鋭い10代の時期にいろんな文化に触れたことがマイアさんの人間的なベースになってるんじゃないかとも思うんですけど。
マイア・バルー:絶対あると思います。しかも、ただの旅じゃなくて毎回その国の人に会って、その土地の人と関わるじゃないですか。ピエールなんて本当にツーリストとして旅することに興味がなくて、毎回必ずそこには友達がいたり、ライブがあったり、一回一回の旅がすごく濃いんですよ。人の家に行って、生活の中に入りこんでいくんですね。だから、今でもいわゆる観光旅行ってできないですもんね。私もそういう旅を通していろんな国の価値観と出会いの素晴らしさを実感したし、その感覚がベーシックにあることは間違いないです。
そうしたなかで自分のアイデンティティについて考えることもあった?
マイア・バルー:たぶんあったと思う。もちろん仮にハーフじゃなかったとしても、誰しもあるじゃないですか。私の場合パリでも日本語で勉強してきたし、日本人学校にも行っていたけど、帰国してからすごい違和感があって。「日本人は何を考えているかわからないから、むかつく」みたいな(笑)。「私、超パリジェンヌ!」みたいな感じ(笑)。ものすごくイヤな感じだったと思う。そのころ私に会った人は今でも言うもんね、「おまえ、あのとき最悪だったな」って(笑)。たぶん、あのときはわからないから否定しちゃってたんだと思います。でも、日本人とバンドを組んだり、音楽で関わることで、最初に気になっていた点がまったく気にならなくなっていった。だから、自分は何人でどこにいたらいいのか、何をしたらいいのか、悩んでいた時期もあったけど、あんまりブレることはなかった。やっぱりね、私には出会いと音楽があったから本当にラッキーだったと思う。
フルートを吹き始めた時期はどんな音楽をやってたんですか。
マイア・バルー:最初は東京でクラシックを勉強してたんですけど、英語を勉強しにバンクーバーに行った時期があって、そのときはジャズのビッグバンドに入ってました。私がすごく好きなガーシュインの“ラプソディー・イン ・ブルー”とかをやっていて、そのときに「人と一緒に音を奏でるって、なんて楽しいことなんだろう!」って思って。人と音楽を通していろんな出会いがあって、「これに越したことはない!」って思うようになったんですね。まさに「これだ!」って感じ。それで、本当は日本の高校に戻るはずだったんだけど、中退しちゃったんですよ。大学検定のために自分のリズムで勉強しながら、17、18歳からは東京でライブに行くようにもなって、(シャンソン歌手の戸川昌子が経営している渋谷のシャンソニエ)『青い部屋』に行くようになって、ちんどんと知り合って、バンドに入って……っていう感じですね。
日本に帰ってきて最初にやり始めたのはどういうバンドだったんですか。
マイア・バルー:最初の最初は、戸川昌子さんの息子がロック・シャンソンみたいなバンドをやっていて、そのなかでフルートを吹いてたんですよ。歌うようになったのは随分後、ここ3年ぐらい。
かぼちゃ商会に入ったのはいつごろ?
マイア・バルー:18歳のときですね。わりと日本に帰ってきてすぐ。彼らの音楽とか世界観に惚れ込んで、すぐに入れてもらったんです。
どういうところに惚れ込んだんですか。
マイア・バルー:音楽のどこが好きか説明するのは難しいけど、ツボにハマったんですね。私はフランスの音楽がベーシックにあるから、ちんどんとか全然わかってないんですよ。でも、そこにある楽しい雰囲気と独特の妖しさにハマったんでしょうね。悲しいけれどなんか楽しい、みたいなところにも人間くささを感じて。私はサーカスの音楽とかワルツもすごく好きなんですけど、ヨーロッパのストリートの音楽とちんどんがリンクして。ジプシーの音楽にも通じるところがあるしね。
2007年には『くさまくら』というコンピをプロデュースされましたね。ここには奄美の唄者の方やアイヌのトンコリ奏者であるOKIさん、それにかぼちゃ商会や戸川昌子さんも収録されていますが、これってある種の“ディスカバリー・ジャパン”のようなものだと思うんですよ。こういう方向に意識が向いていったのはどういうきっかけだったんですか。
マイア・バルー:『青い部屋』にはすっごくおもしろいバンドが毎日出ていて、ここに入っているのはそこで出会った人がほとんどです。『青い部屋』では人間的にも音楽的にもいろんな出会いがありましたね。日本にこんな豊かで個性的な音楽があるなんて!と驚いちゃったんですよ。「これはもう日本にしかない!」と思ったし、フランス人が見ても絶対感動するだろうと。「日仏ハーフとしてなんとかしないと」っていう使命感からやったんだと思います。
そもそも戸川さんとの出会いは?
マイア・バルー:昔からピエールと昌子が仲良かったから。本当に小さいころから晶子のピアスや付けまつげを引っ張ったりしていたので(笑)、第二のママみたいな存在ですね。彼女とは今も仲良くしているし、彼女のパンキッシュな精神は最高だと思います。『青い部屋』ではストリップの日からジャズの日からメタルまであって、いろんな音楽と出会って。『青い部屋』の存在は私にとってすごく大きかったと思いますね。
ご自分のバンドを作って動き始めたのが22、3歳ぐらいのころですね。
マイア・バルー:そうですね。そのときはまだ何をやりたいのかよくわかってなかったと思うけど、ただ、歌いたい歌がいくつかあったんです。それを徐々に形にすることで自分の世界が見えてきた。ビジョンとしてあったのは、ベースと2人だけでやりたいということ。それまでやってたちんどんはメンバーの人数も多かったし、人数が多いための自由/不自由もけっこう見えてて。だから、なるべく少ない人数・少ない音で、どこまでできるか。それでもともとかぼちゃ商会のチューバをやってたAbuと2人で始めたんだよね。まずはピエールやビーアの曲をカバーしてみたり。自分で作曲した曲もあったけど、それだけでライブをするほどの量もなかったから。私はリスク好きなところがあって、リハを始めてすぐにツアーやライブを入れちゃうんですよ(笑)。それもゴールデン街のバーとか畳2畳のスペースを使ったお座敷ライブとか(笑)。そうしたなかでだんだん世界を広げていきたくなったころに、パーカッションの(駒澤)れおと会って。そのころから「こういう音に仕上げよう」っていう考えがまったくなかったからすごく自由だったし、曲によっても全然方向が違ってた。だから、結果的にジプシー・タンゴ ・ジャパニーズになってたりね。料理でいうと、その場で塩を入れて、唐辛子を入れて、ブルドックソースを入れたらこうなっちゃった、みたいな感じ(笑)。
“こういう料理を作ろう”っていうんじゃなくて、“このスパイスとこのスパイスが好きだから入れちゃえ!”みたいな感覚?
マイア・バルー:そうそう!もちろん、後からこれはトゥーマッチだったかなって思うこともあったけど、若いときって大抵トゥーマッチなぐらいやりたくなっちゃうじゃないですか。それが大人になって、ちょっとづつ選別していくようになった。
そうした作り方は今も変わらない?
マイア・バルー:そうですね。今もジャンルには囚われてないし。なんか、最近わかってきたのは、「私がやりたいのは都会的でプリミティブなサウンドなんだな」っていうぐらいで。だからといってそのヒントを元に作るわけでもないし、今でもそういうことはあんまり意識しないですね。言い方を変えれば、自分のベーシックを大事にしながら、新しいものに挑戦していく。「これは圧倒的にマイアの世界だね」ってものを作りたい。でも、難しいものにもしたくない。ポピュラーなものにはしたいけどいっぺん聴いたら旋律が残るようにはしたいし、そういう意味ではポップにしたいけど、やっぱり個性的なものを作りたいとも思ってて。でもね、例えば「マイアの音楽ってすごく個性的だよね」って言われたとしても、私にとってはどこかで聴いて、自分のなかで消化してて出てきたものが多いんですよ。どこかでいろんなものに影響されてると思うし、「ひとりでゼロから全部作ったんだよ」とは絶対に言えない。
ただ、スパイスの調合具合でマイアさんならではの味になればいい?
マイア・バルー:そうそう、そうだと思う。「これとこれを混ぜよう」と思ったのは私の感性だから。でも、素になったものは新しくもなんともないものだと思うし。これだけいろんな音楽があるから、本当に新しい音楽を作るのは難しい。今はミックスの時代だと思うんです。そもそも、いろんな人たちがミックスするところから文化とか文明って生まれてくると思うんですよ。
ところで、11月3日(水)の“Hennessy artistry Presents J-WAVE Gilles Peterson’s “WORLDWIDE SHOWCASE 2010”~Galaxy Session~”では、シロ・バプティスタと競演されますね。
マイア・バルー:そうですね。私もすごく楽しみですね。日本で活動していると、フランスに行っても出会えないフランス人と一緒にやる機会があったり、ニューヨークに行っても会えなかったシロと競演できたりして、すごくおもしろくなってきましたね。彼はただのパーカッショニストじゃないから、どうくるかまったく想像がつかない。そこが楽しみですね。私もまったく想像できないし、シロもできないだろうし、そういう意味ではハプニングが多いと思います。
マイアさんこれまで数々のセッションを繰り広げてきましたが、セッションのおもしろさってどういうところにあるんでしょう?
マイア・バルー:人生セッションだと思っているし、それがあるから音楽を続けていられる。セッションがなかったら続けてないかもしれない。音楽を通じた人との出会いってやっぱりおもしろいですからね。言葉が通じなくても通じ合えるわけだし、セッションを通して自分を再発見することも多いし。いろんな人とやることで自分も変化するし、「危ない扉が開いたぞ」って思うこともあるから。
まさにコミュニケーションですね。音で会話するような。
マイア・バルー:ライブもセッションだから。こっちが毎回決まりきったことをやったとしても、お客さんとのセッション、見えないやりとり、ギブ&テイクがあるから、やっぱり毎回違うんですよ。これからの人生だって、誰と出会って、どういう風にその出会いが展開するなんてわからない。そういう楽しみですよね。セッションがなかったら人生つまらないですよね。
“Hennessy artistry Presents J-WAVE Gilles Peterson’s “WORLDWIDE SHOWCASE 2010”~Galaxy Session~”の詳しい情報はこちら
デビューアルバム「地球をとってよ!」好評発売中 [amazon.co.jpで購入]
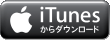
オフィシャルサイト:www.maia-zoku.com/
この記事へのつぶやき
- タイムアウト東京について/プレスリリース |
- 採用情報 |
- 情報提供 |
- 広告について |
- モバイル版 |
- 利用規約/免責事項 |
- プライバシーポリシー |
- コンタクト
Copyright © 2014 Time Out Tokyo

















コメント